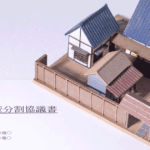目次
はじめに
「自分が亡くなった後、不動産を孫に遺したい」と考える方は少なくありません。孫の将来を思い、自宅や土地を直接引き継がせたいと考えるのは自然なことです。
しかし、孫は原則として法定相続人ではありません。そのため、何も対策をしなければ、孫が不動産を受け継ぐことができないケースもあります。方法を誤ると他の相続人とのトラブルや、孫に重い税負担が生じる恐れもあるため、孫に不動産を受け継がせたいなら事前に専門家に相談しておくことが大切です。
本記事では、孫に不動産を受け継ぐ方法や、その際に発生する税金、注意点などを解説します。
第1章 孫に不動産を相続させる(遺贈する)方法
孫に不動産を遺したいと考えた場合、状況によって選べる方法は異なります。重要なのは、「孫が相続人になるケース」と、「相続とは別の方法によって不動産を譲るケース」がある点です。ここでは、孫に不動産を相続させる(遺贈する)方法を解説します。
1-1 代襲相続|子が先に亡くなっている
被相続人の子が、相続開始前にすでに亡くなっている場合、その子に代わって孫が相続人となる制度を代襲相続と言います。代襲相続が成立する場合、孫は法定相続人として不動産を相続します。そのため、遺言書がなくても、法定相続分に基づいて不動産を引き継ぐことが可能です。
代襲相続における相続割合は、本来その子が受け取るはずだった相続分を、孫が引き継ぐという考え方が基本です。例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる家族構成で、そのうち1人の子がすでに亡くなっている場合、法定相続分は配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちで分ける形になります。
このケースでは、生存している子が4分の1、亡くなっている子の相続分も4分の1となり、その4分の1を孫が代わって相続します。孫が1人であれば、その孫が4分の1をそのまま相続することになります。
一方、亡くなっている子に孫が2人いる場合には、その4分の1を2人で分けることになり、孫1人あたりの相続分は8分の1ずつです。このように、代襲相続では子の取り分を基準に、孫の相続割合が決まります。
なお、子が生存している場合には、将来の希望として「孫に相続させたい」と考えていたとしても、代襲相続は成立しません。代襲相続は、一定の条件を満たした場合にのみ認められる制度であることを理解しておくことが大切です。
1-2 再転相続|子が相続の承認・放棄を選択する前に亡くなった
被相続人が亡くなった後、相続人である子が相続を承認するか放棄するかを決める前に亡くなった場合には、再転相続が発生します。この場合、一次相続(被相続人→子)の相続権が孫に引き継がれる「二次相続」が生じ、結果的に孫が不動産を相続することになります。
また、再転相続が生じた場合、孫は被相続人の子(自身の親)への一次相続について承認するか放棄するかを選択すると同時に、自身への二次相続についても承認または放棄を判断しなければなりません。ただし、これらの選択は自由に組み合わせられるわけではない点に注意が必要です。
相続の承認・放棄の選択権は自身を起点に遡って行使する形になるため、自身への二次相続を放棄したなら、一次相続を承認することはできません(二次相続を放棄した時点で、一次相続については関係がなくなるためです)。一方で、祖父母から子への一次相続を放棄したうえで、自身の親から自身への相続のみを承認することや、両方の相続を放棄することは可能です。
1-3 養子縁組|孫養子にする
養子縁組をすると、孫は法律上の子となり、他の子と同じ立場で法定相続人になります。そのため、孫は法定相続分に基づいて不動産を相続することが可能です。
この方法は、実の親が存命であっても選択できます。養子縁組をしたからといって生活環境が変わるわけではなく、これまで通り実の親と暮らし続けることも可能です。また、相続が発生した際の相続分についても、実子と区別されることはありません。
一方で、養子縁組は相続税の計算にも影響します。法定相続人が増えることで基礎控除額が広がり、税負担を抑えられる可能性がありますが、税制上は無制限に養子をカウントできるわけではありません。
被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合でも2人までしか、税務上の法定相続人の数として扱われない点には注意が必要です。また、後述しますが、養子縁組の場合は相続税の2割加算にも注意しましょう。
1-4 遺贈|遺言書に不動産の相続人を孫と記載する
祖父母が遺言書を作成し、不動産を受け取る相手として孫を指定すれば、孫はその不動産を取得できます。このように、遺言によって財産と取得する人を定める行為を遺贈と言います。
遺贈は、配偶者や子といった法定相続人に限らず、孫のように相続人ではない人に対しても行うことが可能です。そのため、子が存命であっても、孫に不動産を遺したい場合の有効な手段と言えるでしょう。
ただし、遺贈によって不動産を取得した場合、相続によって取得するケースと比べて、税金の負担が重くなる点には注意が必要です。特に、固定資産税評価額が高い不動産ほど、孫が負担する税額も大きくなる傾向があります。
遺贈を検討する際は、想いだけで判断せず、税金や他の相続人への影響も踏まえたうえで進めることが大切です。
1-5 死因贈与|死亡後に不動産を孫に贈与する契約を結ぶ
孫に不動産を遺す方法として、死因贈与を選ぶケースもあります。死因贈与とは、「自分が亡くなった時に不動産を孫に贈与する」という内容の契約を、生前に結んでおく方法です。
死因贈与は遺言と似ていますが、贈与契約である点が異なります。死因贈与は口約束でも成立しますが、後々のトラブルを防ぐためにも公正証書に残しておきましょう。
また、死因贈与によって不動産を取得した場合も、相続による取得と比べて税負担が重くなる点には注意が必要です。遺贈と同様に、固定資産税評価額が高い不動産ほど、孫の負担が大きくなります。
第2章 孫に不動産を相続させる(遺贈する)際に発生する税金
ここでは、孫に不動産を受け継ぐ際に発生する税金について解説します。
2-1 相続税
孫が相続や遺贈、死因贈与によって不動産を取得した場合、相続税が課せられる可能性があります。相続税は、不動産だけではなく、相続によって取得した財産の合計額に対して計算される点が特徴です。
まず、被相続人の遺産総額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、この金額を超えた部分について相続税がかかります。
次に、基礎控除後の課税遺産総額を、いったん法定相続分で分けたものとして相続税の総額を算出します。そのうえで、実際に不動産を取得した人が、その取得割合に応じて相続税を負担する仕組みです。
例えば、法定相続人が子1人と孫2人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。この場合において課税遺産総額が4,000万円であれば、課税遺産総額が基礎控除額を下回るため、相続税はかかりません。
一方で、同じく法定相続人が子1人と孫2人の場合において、課税遺産総額が6,000万円なら、基礎控除額4,800万円との差額の1,200万円が課税対象になります。この1,200万円について、いったん法定相続分で分けたものとして相続税の総額を計算し、その後、財産の取得割合に応じて相続税を負担することになります。
このように、相続税は不動産の評価額だけで単純に決まるものではなく、相続人の人数や不動産以外の遺産額などで変わります。また、不動産の評価額の算出方法や特例の適用によっても税額が異なるうえに計算方法も複雑なので、算出する際は税理士への相談がおすすめです。
2-2 不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県から課される税金です。相続の場合は課税されませんが、死因贈与や法定相続人以外への遺贈の場合は不動産取得税がかかるのが原則です。ただし、「土地の◯割を与える」といった包括遺贈であれば、相続人以外への遺贈でも不動産取得税は発生しません。
また、不動産取得税は、「固定資産税評価額×税率」という考え方で算出されます。例えば、固定資産税評価額が3,000万円の不動産を取得し、適用される税率が3%だった場合、不動産取得税は「3,000万円×3%」で計算され、90万円となります。
なお、住宅用不動産に対する軽減措置の内容や適用される税率は、不動産の所在地や自治体によって異なります。実際にどの程度の税負担が生じるのかについては、事前に自治体や専門家へ確認しておくと安心です。
2-3 登録免許税
登録免許税は、不動産の名義を変更する際にかかる税金です。相続や遺贈、死因贈与によって不動産を取得した場合には、所有権移転登記を行う際に登録免許税が発生します。
登録免許税は取得方法によって税率が異なり、相続による所有権移転登記の場合は、固定資産税評価額に対して0.4%の税率が適用されます。一方、遺贈や死因贈与による登記では、原則として2%の税率が適用されるため、相続と比べて負担が大きくなります。
登録免許税の計算方法は、「固定資産税×税率」です。例えば、固定資産税評価額が3,000万円の不動産を相続によって取得した場合、登録免許税は「3,000万円×0.4%」で計算され、12万円となります。一方、遺贈や死因贈与によって取得した場合には、「3,000万円×2%」の60万円です。
第3章 孫に不動産を相続させる(遺贈する)際の注意点
孫に不動産を相続させる(遺贈する)際の注意点は以下の通りです。
3-1 相続税が2割加算されるケースがある
孫が不動産を取得する場合、相続税が通常よりも重くなることがあります。孫養子として相続する場合や、遺贈、死因贈与によって不動産を取得する場合には、原則として相続税が2割加算されます。
2割加算とは、本来計算された相続税額に対して、さらにその2割分が上乗せされる仕組みです。例えば、孫が負担する相続税額が100万円と算出された場合、2割加算により20万円が追加され、実際に納める相続税は120万円となります。
そのため、同じ評価額の不動産であっても、子が取得するケースと比べて、孫が負担する相続税が高くなる可能性があります。孫に不動産を遺したいと考えている場合は、取得方法によって税負担が変わる点に注意が必要です。
一方で、代襲相続や再転相続によって孫が相続人となる場合には、相続税の2割加算は適用されません。孫がどの立場で不動産を取得するのかによって、相続税の扱いが異なることを理解しておくことが大切です。
3-2 他の相続人の遺留分を侵害するリスクがある
遺言や遺贈によって孫に不動産を遺す場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまう恐れがあります。遺留分とは、配偶者や子などの一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。
例えば、不動産を孫に遺贈する内容の遺言を作成した場合、他の相続人が遺留分を侵害されたとして、金銭の支払いを求めてくる可能性があります。孫が不動産を取得できたとしても、後からまとまった金額の支払いが必要になり、トラブルに発展するケースがあるのです。
また、人間関係の悪化を招くリスクもあります。法律上は正当な権利行使であっても、「なぜ孫だけが優先されたのか」といった不満が残り、相続をきっかけに親子や兄弟間の関係が悪化してしまうケースも少なくありません。
特に不動産は分けにくい財産であるため、感情的な対立が生じやすい傾向があります。孫に不動産を遺したい場合には、法的な問題だけでなく、相続後の家族関係まで見据えたうえで、遺言内容や分配方法を検討することが大切です。
まとめ
孫に不動産を遺したいと考えても、孫は原則として法定相続人ではありません。そのため、代襲相続や再転相続が発生するケース以外に孫に不動産を受け継ぎたければ、養子縁組や遺贈、死因贈与などを行う必要があります。
また、どの方法を選ぶかによって、相続税の2割加算の有無や、不動産取得税、登録免許税といった税負担、さらには他の相続人との関係にも違いが生じます。特に、遺留分への配慮が不足すると、相続をきっかけに家族関係が悪化してしまう恐れもあります。
孫に不動産を遺す相続対策を成功させるためには、「誰に遺すか」だけでなく、「どの方法で遺すか」まで含めて検討することが大切です。税金や登記、相続後のトラブルを防ぐためにも、早い段階で司法書士や不動産会社などに相談し、自分の状況に合った相続対策を整理しておくと安心でしょう。
住まいの賢者では、司法書士法人と連携する不動産会社として、相続方法の検討から登記手続き、不動産の活用や売却に関するご相談まで、相続対策を一体的にサポートしています。孫に不動産を遺したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
不動産の無料相談なら
あんしんリーガルへ
電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。
孫への不動産相続に関してよくある質問
ここでは、孫に不動産を遺すことを考えている方の頻出質問に回答します。
遺言書があれば、孫に不動産を相続させることはできますか?
遺言書があれば孫に不動産を受け継がせることは可能です。ただし、孫は原則として法定相続人ではないため、この場合は相続ではなく遺贈という扱いになります。
遺言書に不動産を取得する相手として孫を明記すれば、孫はその不動産を取得できますが、相続税の2割加算や、不動産取得税、登録免許税の税率など、相続とは異なる点があることに注意が必要です。また、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、後からトラブルに発展する可能性もあります。
孫に不動産を残すために、今からできることは何ですか?
まずは、自分の家族構成や財産の内容を整理し、孫に不動産を遺す方法としてどの選択肢が適しているかを確認しましょう。代襲相続が想定されるのか、遺贈や死因贈与を検討すべきなのかによって、準備すべき内容が異なるためです。また、遺言書の作成や、税金・登記の扱いを把握しておけば、相続発生後に孫にかかる負担やトラブルを減らせるでしょう。